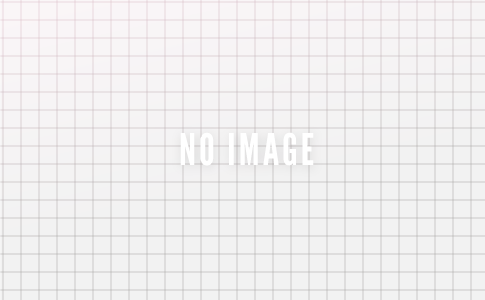「麻雀放浪記」の完結から新撰組の誕生まで、いわば新撰組前夜といってもいいものだが、この間に何があったかというと、まず放浪記を単行本にして出版した時の爆発的な売れ行き。これはもう場外ホームランそのものだったように思われる。
そうなると出版サイドの考えることは2匹目、3匹目のドジョウ。即ち、放浪記の続編だけではなく、これをシリーズ化したらどうかというもの。ヒット商品を産み出した時の企業サイドの常套手段でもある。
さっそく阿佐田氏に交渉。はたして阿佐田氏は二つ返事でひき受けただろうか。まず、考えたに違いないことは第1作の放浪記を凌ぐほどのものが書けるかということ。
放浪記の背景となった年代はいわゆる敗戦直後の昭和20年代で、アサ哲こと坊や哲はまだはたち前の少年。
焼け跡がそこかしこに残る東京・上野界隈では、バラック小屋の中で互いを喰い合うような鉄火場が開帳されたりもしていた。
そこに吸い寄せられるようにしてやってきた見たこともないクセモノたち。この時代ならではの役者たちだ。
阿佐田氏は第1作の放浪記で、かけがえのない貴重な材料をすべて使い切っていたのである。
放浪記を凌ぐような麻雀小説はもう2度と書けない、とそこまで思っていたのではないだろうか。
時代もどんどん変わり、自動車の普及とともに裏技も仕事師も遠い昔の話となって、ほとんどの人にピンとこない世界に変わりつつあった。
たとえ第1作めの放浪記と変わらないレベルの麻雀小説が書けたとしても、それを読んだ読者のみなさんはどのように感じるだろうか。第1作めがあまりにも傑作であったため、似たような味つけでは無意識のうちに、評価をどうしても割びき、気持ち辛めになって「うーん、どうなのかなァ」といったようなことになりはしないか。
書いてもどうせ二番煎じの域を出ないと思えば、阿佐田氏も出版サイドの要請に対しかなり渋ったに違いない。
それでもこれまでの付き合い上、ひき受けざるをえなかった。とにかく書いてみようか、と思ったに違いない。
しかしその一方で、どうすれば1作めを超えるものが書けるのかという想いが阿佐田氏の胸に宿りはじめたに違いない。とっておきの手材料はすべて使いきってしまったので、それ以上のものは何も残っていない。
こんな時、職業作家たちはどんなことを考えるか。
新しいストーリーを案出すればいいわけだから、そんなもん、時間さえかければなんとでもなるだろうということで、ああでもない、こうでもないとのた打ちはじめる。
この悪戦苦闘はまさに地獄絵図そのもので、やっとの思いで書き上げた時は、げっそりと痩せていたりする。
しかも、こんなくそ面白くもないものッ、と思うのは読者ではなく、当のご本人。にぎり潰し、屑かごに投げ入れてしまう。
次善の策がないわけではない。現場とおぼしきところにおもむき、取材するという手があるが、これには運・不運がともない、収穫なしの空振りも。
阿佐田氏が思い浮かべた現場はマージャン・クラブであろうが、この時同氏は40歳をこえたばかり。しかし、若いころと違って体躯のほうは、関取りかと思えるほどの太鼓腹に、髪は関ヶ原の生き残りのようなざんばら髪。
こんな男がヌーとはいってきたら、マージャン屋のおやじ、思わず腰を浮かしたに違いない。