竹書房の対局室に居た私にかかってきたアサ哲の電話は自宅からのものではなく、鳥取からのものだった。
こんなことは初めてだったので一瞬受話器を握りしめたが、アサ哲の口調は全くいつもと変わらず、「ヒマならば遊びにいらっしゃい」というもの。
私はアサ哲が鳥取に行ってることも知らなかった。また、なぜ鳥取なのかと訊きもしなかった。招待されたからには四の五の言わず、とにかく駆けつけるのが先決。
その日の出発は時間的にも無理だったので、翌日、私は羽田から鳥取へと飛び立った。東京に居た時は不覚にも気づいていなかったが、この時の3月、鳥取は大雪に見舞われていた。
そして鳥取空港の上空にやってきて、いよいよ降下かと思ったその時、思いもかけないアナウンス。「降雪のためこの空港には着陸できません。これから大阪国際空港に向かいますので・・・」
私としてはこの現実を素直に受け止め、次善の策を考え出すしかなかった。これしかないだろうという手段は列車に乗り換えること。いろいろな人に、なんとか鳥取に行く列車に乗ることができた。山を越えて行く列車だったので、高みに差しかかると箱根登山鉄道のようにスイッチ・バックしたりした。
そして数時間後、ついに到着。陽はとっくに落ちていてほとんど真夜中みたいな時間だったが、宿に着いた時、アサ哲はまだ起きていた。
報告がてらいろいろ話しているうちに、アサ哲のほうの事情もわかってきた。夫人同伴で来ていたそうだが、夫人に急きょ東京に戻らなければならない用事が出来たそうでそこで私への呼び出しとなった。
つまり、もう少し旅を続けたいから、キミなら付き合ってくれるンじゃないか、ということのようだ。
それにしても止宿した部屋の立派なこと。完全に離れになっていて、普段は使われていないとのこと。賓客でなければ泊まれない部屋だったのである。
「江国さんの紹介なんだ」とアサ哲。なるほどと納得。随筆家の江国滋氏(1934-1997)は新撰組の月例会にも顔を出してくれる人で、知識人ならではの手堅いマージャンの打ち手であった。
一夜明け、まずは宿を出ることになったが、どこへ行くかなどアサ哲はまだ決めていたかった。どこもかしこも雪が積もっていたので歩くこともままならず、とりあえずめしでも喰おうということで一軒の店にはいった。
壁に貼り出されたメニューは今が蟹のシーズンであることがひと目でわかるようになっていた。
「蟹ってやつは、人間に食べられるために生まれてきたようなもンだな」とアサ哲。
メニューの中で私の眼をひいたのは食べたことのない「焼き蟹」。むさぼるようにして両手をフル稼働させたが、味はむろんのこと、それ以上に私を無口にさせたのが焼き蟹の香り。たとえようもなく香ばしく、この香りだけを土産にしたいほどだった。
















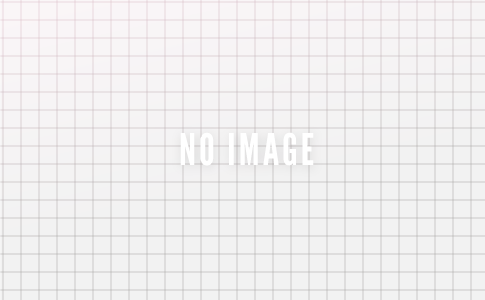
コメントを残す