アサ哲には調度品にこだわるようなところはまったくなかった。だからあのピカピカのおでん鍋は到来物のひとつであった可能性の方が高いことになる。しかし、アサ哲の実体を書き残すためには、推測ごとは極力避けたいところ。それには本人の肉声を聴くのが一番だが、それに近いものがある。荻窪時代、月刊誌に書いた連載物(2回)だが、通しのタイトルは「三博四食五眠」(「小説CLUB」桃園書房)。
テーマは喰い物に関してのエッセイだが、いわゆるグルメ本とか食通の蘊蓄噺などとはまるで違い、新連載の初っ端からいきなりの型破りで始まっていた。
そのタイトルは「思い出の食べ物ワースト3」。
舞台になっているのは終戦前後の昭和20年あたり。
かぼちゃの粉、大豆の豆粕が固い板状になったもの、そして3番目がトウガラシソバ、この3点が最悪の喰い物ということだが、今の人たちにはおそらく想像もできないシロモノではなかろうか。
当時、何か食べ物を買おうにもそのような店がなかったご時世だから、配給という形で来るものを口にするしかなかったのだ。
しかしトウガラシソバだけは配給品ではなく、アサ哲たちが考えた喰い方。尋常ではない量のトウガラシをカケソバに入れ、それを一気にかき込むというものだが、これはタダではすまなかった。ある時、新宿の裏街で呑んでいた時、アサ哲にカラオケのマイクがまわってきたが、アサ哲は手を軽く振ってこれを断った。
そして私にこんなことを言った。「トウガラシ中毒で喉をやられてね、声が出ないンだよ」。
アサ哲と本名の色川武大名では数多くの作品が世に出ているが、自身の来し方を自身の言葉で語ったものはほとんどなく、その点でこの連載物はヒジョーに貴重なものといえるのではなかろうか。
食べ物がテーマのこの連載だが、アサ哲はその係わり方をこのように書いている。
『私は食通でもなんでもないし、食べ物など各人の好みもあり、軽々しくほめたたえる気もないが、(略)』
そしてアサ哲が過ごした特殊な少年期。まるでアサ哲の原点を示すかのように、ここから始めなければオレと喰い物のことは語れない、と言ってるかのようだ。
昭和4年生まれのアサ哲は中学時代、停学処分を受けているが、そのことにも触れていて、『私は空襲さかんなりし頃に、自分たちの同人雑誌が摘発されて、中学を無期停学になっており、(無期停学は退学よりも重くて他の学校に転向もできなかった)非国民の烙印を押されて家の中に謹慎していなければならなかった。』
摘発した官憲としては「文芸などにうつつをヌカしている時代かッ」ということで見せしめの意もあってのことだろう。
家の中に幽閉状態となったアサ哲。その毎日は実に悲惨なもので、進学もできず、工場街に足を踏み入れることもならないため、徴用にもとられない。(徴用とは「国家権力により国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること。」広辞苑)
さらに友だちとは断絶、この世の誰も、優しい眼を向けてくれる者はいない、といったように、14、5才の少年にはもうどうしていいかわからないことになってしまった。
しかし陽はまた昇るで、このあとにやってきたのが“終戦”という夜明け。アサ哲もホッと息を吹き返した。















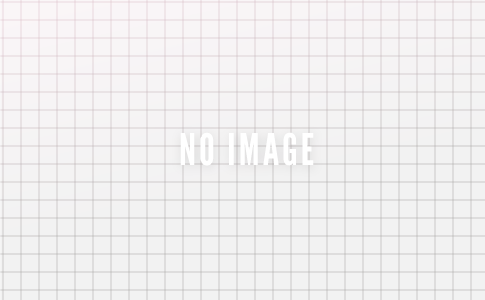
コメントを残す