いわゆるアサ哲番のような編集者・関係者たちがなんとなくその場で輪が出来た時など、中心に居るアサ哲としては夫人が不在ということも多々あったので、「たまには浅草にでも行ってみるか」ということになる。
外に出掛ける時は新宿がほとんどで、浅草方面はめずらしい。ところがめずらしいだけの浅草行ではなくなってきたのである。
まず最初に行ったのはさくら鍋の老舗(しにせ)。要するに馬肉のすき焼きを食べたわけだが、私より若い人を含め、数人はいたかと思う。話がはずんでいたこともあって当然かなりの量を食べたと思われる。
ところが浅草はアサ哲にとっては懐旧の土地でもあるので、わずか1軒だけですむはずがなかった。腹ごなしに、というようなことで次に立ち寄ったのがかの有名な「神谷バー」。ワイワイ騒ぎながら電気ブランなどを呑みまくった。
「三博四食五眠」の中にもオソロシイ箇所があった。いささ長いので引用はしかねるが、「上野へつくとまっさきに“蓬莱屋”のかつを喰いに行く。」からはじまり、このあと、「串カツを揚げて貰って酒を軽く呑み、とんかつでごはんを喰う。」
しかしこれだけでは終わらないのがアサ哲の凄いところで、とんかつでごはんを食べたあとにもかかわらず、すぐそばにあるもう一軒のカツ屋にとび込むのである。
さらにめったに来ない以上、このパン屋の前を素通りするわけにはいかないとか、人情の塊を通りこして化け物のような行動に出るのである。
浅草行のこの時もそうだった。3軒目め4軒めなどは焼き鳥屋だったのか軍鶏(シャモ)鍋屋だったのかも今では定かでないが、とにかく半日以上の強行軍になったのは確かなところ。
アサ哲自身、はじめからそのようなことを考えていたとはとても思えないが、なじみにあった土地柄だけに、歩いているうち、次々と以前の記憶がよみ返ってきたのではないだろうか。
そしてしめくくりは根岸の寿し屋。二階もあるような大きな店構えだったが、それだけではなかった。板前さんび数も相当なもので、いわばマンツーマンのような格好で握ってくれるのである。
ところが食欲旺盛であるはずの若手勢は誰ひとり、注文を出そうとしない。それも無理はない。すでに満腹状態を通りこし、ギブアップの白旗を掲げていたのである。
私もほぼおなじような状態ではあったが、好きなものを一貫か二貫は口にした。
ひとり悠然と寿しをつまんでいたのはどこ吹く風のアサ哲だけ。恐れ入りましたと手をつくしかなかった。
この地獄喰い歩きのあともアサ哲と街に出ることはあったが、あのように凄まじいものはなかった。この頃の年格好はアサ哲が40台の半ばで私も30台の半ばあたり。
新宿のゴールデン街にアサ哲と出かけた時、ある小さなバーで別のグループに出会った。作家の佐木隆三氏と編集者たちが、この時は直木賞受賞の二次会だったようだ。佐木氏の直木賞といえば映画化もされた「復讐するは我にあり」のことで、昭和50年(1975)に受賞している。
このように想い返してみると、ますます新撰組のシの字も出なくなってくるが、アサ哲からは音沙汰が切れかけ時に電話がやってくる。
その時は竹書房の対局室に居た。例のマージャンに誘う時のような笑いを含んだ声だった。「ご自宅ですか」と問い返すと、「いやァそれがね、今、鳥取にいるんだ」と応えた。東京だって島根だっていっしょじゃないか、と言わんばかりの軽い口調で。はたして、どのようなことになるのか。















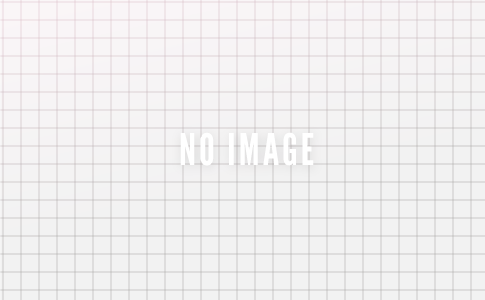
コメントを残す