鳥取の次は列車に乗り城崎(きのさき)で降りた。温泉で有名な街だが、アサ哲の頭の中にはむしろ志賀直哉氏の小品「城崎にて」があったかもしれない。
止宿した宿はここも江国氏のおすすめによるものか、お城のように重厚な造りだった。
さてこの後はどうするかだが、アサ哲からの提案で金沢にでも行ってみるかということになった。山陰線で京都に向かう途中、急に車内が明るくなった。余部(あまるべ)鉄橋にさしかかったのだ。
「おい、オレは高所恐怖症なんだぞ」。アサ哲がもそもそ言いながらバックの中から年季の入った小型のカメラを取り出し、窓外の景色にシャッターを押しはじめた。
アサ哲が機械類を苦手にしていないことは以前から気が付いていたが、アサ哲がカメラを扱っているのを見たのは後にも先にもこの時がはじめて。
余部鉄橋は後の1986年に列車転落事故を起こし、6人が犠牲になっている。なにしろ高さが約40メートルほどの建造物だけに、この事故後、架け替え案が出てきて工事にはいったのも当然の成り行きだろう。アサ哲が急にカメラを取り出したのは、もともとそのような趣味があったからとは、私には到底思えない。アシスタント、または書生といったようなことをアサ哲の下で何年にも渡りやってきた私なので、あるかないかの判断くらいはかなりの自信で言いきれる。
ではホントのところはどういうことなのかというと、いつか書くであろう作品に対するメモ代わり、というのが私の見立てである。
後年、アサ哲と四国めぐりの旅に出た時、高知でお酌のお姐さんたちに“箸拳”なるお座敷遊びを教えてもらったが、この時もアサ哲は何事かを素早くメモしていた。
メモというのは紙片に文字を書くだけではなく、映像という形で残したり、あるいは録音テープにディテールを保存しておくという手もあったりする。職業作家には常にそのような意識が本能のように植えつけられているのだろう。
いささか理解しにくいのは“高所恐怖症”の方で、私の友人がその典型例を見せてくれたことがある。
吊り橋を渡っている時だった。怖い怖いといいながらも、へっぴり腰でなんとか渡りきるかに見えたその時、友人の一人が笑いながら吊り橋を揺らした。
とたんに恐怖症の友人はあられもない悲鳴を上げただけでなく、その場に固まってしまった。あと一歩か二歩で渡りきるという、いわばゴール寸前の位置でのこと。
一方アサ哲のほうは、視界がいきなり空中のド真ン中に投げ出されたにもかかわらず、おもむろにカメラを取り出してシャッターを切りはじめたのだから、どこが“高所恐怖症”なのかと訊きたくもなる。
アサ哲いわく「平らな処に居てもだね、遥か地平線のあたりに連なる山岳が見えたりすると、もうそれだけで気持ちが落ち着かなくなる」。
私としてはそれ以上付いていけず「・・・」。
















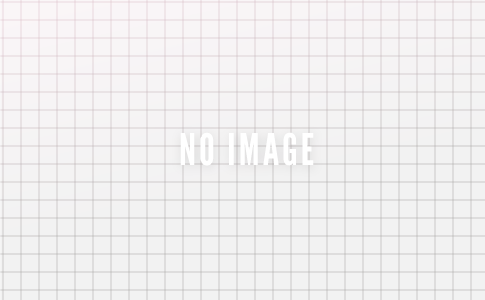
コメントを残す