荻窪時代、アサ哲からは度々電話がかかってきた。その声はハナから笑いをかみ殺したようなところがあって、そのパターンはいつも決まっていた。「もうすぐ○○さんが来るって言ってるンだが、キミはどうかね」。
マージャンの誘いなのだ。私に否応などあるはずもなくいつもいつも矢のように素っ飛んで行った。しかし、ネギを背負ってきたような大甘はひとりも居らず、みんなそれなりの打ち手ばかりだった。
顔ぶれも固定化することなく、年齢層も若い人は居らず管理職クラスと思える人がほとんどで、麻雀新撰組が話題に出てくることもなかった。
今、あの頃のことを振り返ってみると、あの阿佐田邸のマージャンがアサ哲にとっての“取材現場”ではなかったのか、と思えてならない。
アサ哲には街中の取材現場を断念せざるを得ないいくつかの事情があったように思われる。
ひとつは目立ちすぎる体型と風貌。しかも、最初の頃は大きなサングラスをかけた写真しか載っていなかった「週刊ポスト」の観戦記だったが、それが素顔のものに変わってしまったこと。さらにアサ哲にはナルコレプシー(睡眠発作症)という持病があった。
この持病はマージャンの最中にも時々出てくるが、街中を歩いている時などは電柱にぶつかったこともあるそうで独りで行動するには厄介なものになっていた。
アサ哲のものの考え方はすこぶる自由闊達、融通無礙でもあったので、「街中の取材に行けないのなら、このオレの部屋を取材現場にしたっていいンだぜ」くらいのことは考えたとしてもおかしくない。
アサ哲が私に「東京に出てこないか」と誘ったのも、そんな意図もあったのか、と今にして思う。
ある日のこと、私の塒(ねぐら)に突然アサ哲がやってきた。何事ならんと出てみたが、アサ哲の手には包みがブラ下がっていて、「これをキミに食べさせたくてね」と言った。中身はなんと鯖の刺し身。
鯖は通常煮たり焼いたりして食べていたが、生のものを口にしたことはまるでなかった。鯖は鮮度が落ち易い魚なので、生でもいけるというような鯖を扱っている魚屋はめったにあるものではない。
アサ哲はすぐに引き上げて行ったが、乘り物は競輪選手が乘っているような自転車。それがアサ哲邸のベランダにあったことは知っていたが、私は勝手にトレーニング用のものだと思っていた。
しかし、はじめて食べた鯖の刺し身、その旨かったこと旨かったこと。
アサ哲は「安いよ、安いよ」だけを連発するような魚屋には立ち寄らない。「今日のお奨めは?」と問いかけ、それにしっかり応えてくれるような魚屋を知っているに違いない。昔からの付き合いか、と思ったがそうではなかったことが「三博四食五眠」を読んでみてわかった。
転居したばかりの宮前で、看板も上げていないような小さな魚屋「坂本」を見つけたのである。
ここの御主人もなかなかの傑物で、アサ哲がお奨めの穴子を注文した時、料理を担当するであろう若い夫人に対して、その手順を包み紙に書き、渡していた。
アサ哲邸に行った時、私もその現物を台所で見つけて読んだが、手順はともかく、最後の一行がなんとも心地よく目にとび込んできた。
『◎煮物ちゅうは眼をはなさないこと』
















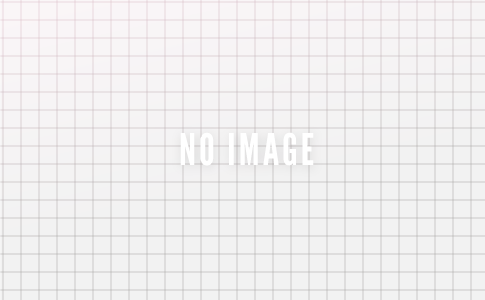
コメントを残す